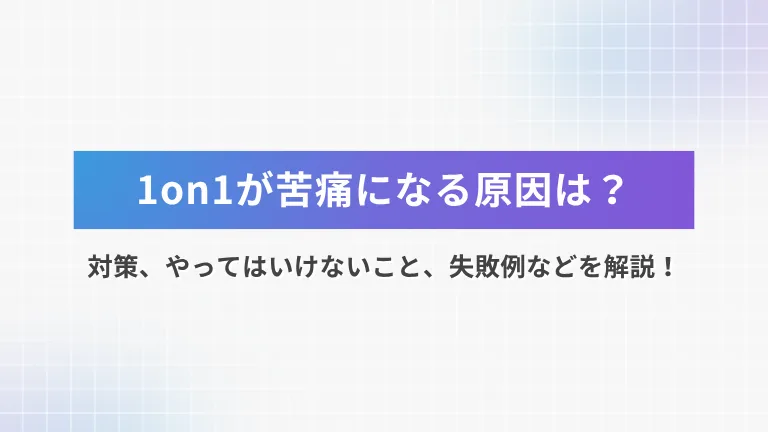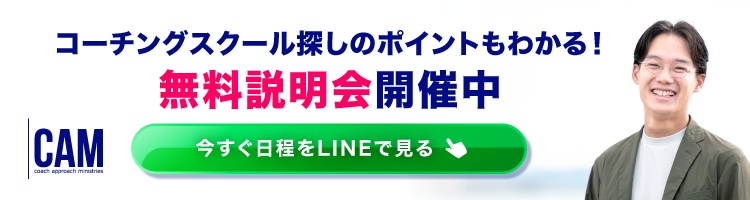1on1は、互いに踏み込んだ会話によって本音を伝え合える重要なコミュニケーション手法です。
ただ、世間では1on1が苦痛、ストレスになって悩んでいる部下やメンバーも少なくありません。
部下やメンバーから1on1が避けられてしまうのには根本的な原因があります。組織やチームで1on1の効果を高めるためにも部下やメンバーに苦痛を与える原因を知ることが重要です。
今回はリーダーやマネージャー、上司に向けて1on1が苦痛になる原因と対策、やってはいけないこと、失敗例などについて解説します。
1on1はそもそも不要なのかという疑問にも回答するので、ぜひ最後までご一読ください。
【この記事でわかること】
- 1on1が苦痛やストレス、嫌いになる原因は、プライベートについて話したくないという思いや怒られるのが怖いことなどが挙げられます。
- 1on1で苦痛を与えないようにするには双方向のコミュニケーションが大前提であり、対策としてコーチングの習得もおすすめです。
- 1on1を苦痛にするやってはいけないことは、ほかの人と比較したり、雑談や説教をしたりすることなどです。
1on1が苦痛、ストレス、嫌いになる原因と対策
1on1が苦痛、ストレスになるのには原因があります。
原因が分からないままだと適切な対策が講じられず、ますます部下やメンバーが1on1を嫌いになるかもしれません。
早速、リーダーやマネージャー、上司に向けて、1on1が苦痛、ストレス、嫌いになる原因を対策も含めて解説します。
原因1.プライベートなことを話したくない
1on1が苦痛になる原因としては、プライベートなことを話したくないという思いが挙げられます。
独身であること、子どもがいないこと、趣味がないことなどに引け目を感じている方は珍しくありません。プライベートなことを聞かれてしまうと、コンプレックスを刺激されるリスクが高まります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規その点、1on1では雑談も生じやすく、ふとしたときにプライベートの話が混ざってしまいがちです。
プライベートを話題にしたがる上司や先輩もいるため、私的なことを知られたくない方にとっては、1on1がストレスになりやすいのでしょう。
【リーダーやマネージャー、上司ができる対策】
1on1では基本的に、部下やメンバーのプライベートについて目上の立場から質問しないのが無難です。もし目上の立場でプライベートなことを話すときは自分のことだけを話題にするのが望ましいといえます。その際に部下やメンバーから私的なことを話し始めるようであれば、自然に聞き役として会話に応じます。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規私的な話題については、部下やメンバーが話したいときに聞くというスタンスを維持すれば、お互いに余計なストレスを与えずに親睦を深められます。
原因2.詰められることがある
1on1は基本的に、部下やメンバーがリーダーやマネージャー、上司に悩みを相談できる機会ですが、詰められて苦痛を感じる場面も珍しくありません。
たとえば、目標の売上に到達しなかった場合や、取引先の商談に失敗してしまった場合などに、感情的に怒られるケースです。
もし、人格を否定する言葉で詰められたら、パワハラだと思われることもあるでしょう。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規部下やメンバーが精神を病んで休職・退職に追い込まれるようであれば、1on1を実施する価値はありません。
【リーダーやマネージャー、上司ができる対策】
リーダーやマネージャー、上司が1on1に参加するときは、一方通行のコミュニケーションを可能な限り控えましょう。一方通行のコミュニケーションは、どうしても対等な関係を損ないやすく、威圧的な命令や指示を生じさせる原因になりやすいです。
反対に双方向のコミュニケーションを成立させることで、部下やメンバーと対等な立場で話しやすくなり、ムードも和やかになってストレスが減ります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規双方向のコミュニケーションを成立させるには、傾聴や質問、承認などのスキルが必要です。
傾聴や質問、承認のスキルを習得したい方は下記の記事を参考にしてみてください。
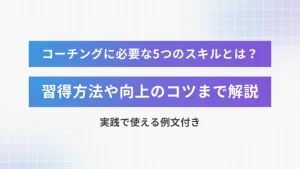
原因3.職場の心理的安全性が低い
1on1が苦痛になる原因として、職場の心理的安全性が低いことも挙げられます。
心理的安全性とは、組織の中で各々の発言が周囲のメンバーに受け入れられるという確信を持てる状態を意味します。
心理的安全性が低い職場では、提案をしても聞いてもらえない雰囲気、トラブルを起こしても報告しづらい雰囲気などが漂います。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規発言が周囲に受け入れられない環境や相談しても助けてもらえない環境が当たり前になると、1on1でも話したいことを話しづらく苦痛を感じるかもしれません。
【リーダーやマネージャー、上司ができる対策】
1on1が苦痛にならないようにするには、心理的安全性を高めるために相手が話しやすい雰囲気を作るのが望ましいです。相手が話しやすい雰囲気を作るために意識したいポイントは下記の通りです。
・「なるほど」「確かに」など共感する言葉を適度に発する
・部下やメンバーの発言を大切にしてメモを取る
・「なぜ~したのですか?」のように責める言い方をしない
・部下やメンバーが話している途中に自分の意見を発してさえぎらない
・部下やメンバーの成果を見つけて称える
・話せる範囲で自分の失敗談を適度に伝える
1つひとつのポイントは特別難しいことではありませんが、積み重なると対話しやすい環境が自然に整います。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規次回の1on1からでもすぐに試せる内容なので、気になったポイントから取り入れてみてはいかがでしょう。
そのほかにも心理的安全性を高める方法はたくさんあります。心理的安全性の概要や高める方法について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
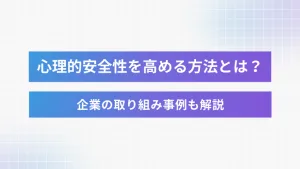
原因4.自信を失っている
自信を失っている部下やメンバーにとって1on1はストレスになりやすいです。
チームでほかの同僚が大きな成果を出していると、劣等感によって萎縮してしまうことがあります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規弱気な姿勢になると、自分の知識や経験、考えに自信が持てなくなり、1on1でも意見や提案を出しづらくなります。
結果として、リーダーやマネージャー、上司の期待に応えられない自分に嫌気がさすと、1on1の時間が苦痛になっても不思議ではありません。
【リーダーやマネージャー、上司ができる対策】
自信の喪失が1on1の苦手要因となっているのであれば、リーダーやマネージャー、上司が、部下やメンバーの長所を見極めて成功体験を積ませることが重要です。
動画編集を趣味としている部下に新卒向けの採用動画の制作を頼んだり、ブログを趣味としているメンバーに会社のブログ運営をお願いしたりします。得意なことであれば成果を出しやすく失敗もしづらいです。
成功体験を積んだ部下やメンバーは、さらに成功体験を積むために成果を出すためのアイデアを考えて実行し始めます。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規提案したいことや報告したい成果が増えるので、1on1が苦手になるどころか楽しみになる可能性もあります。
原因5.話すことがない
1on1で話すことがない点について苦痛やストレスの原因となる場合もあります。
1on1では、業務の生産性を高めるアイデアや組織の課題解決案などについて、意見を求められることがあります。
メンバーや部下の立場としては、定期的に開催される1on1までに話すことを準備しておかなければなりません。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規一生懸命考えても話すことが頭に浮かばず、上司からの期待に応えられないことに落ち込んでしまう部下やメンバーもいるでしょう。
【リーダーやマネージャー、上司ができる対策】
話すことがなくて部下やメンバーが苦痛になるのであれば、1on1のテーマが適していないのかもしれません。1つの話題に固執せずに、部下やメンバーが話しやすいテーマを探ってみましょう。
たとえば、組織の課題についてアイデアが得られない場合でも、業務や人間関係で困っていることがないか問いかければ、悩みを打ち明けてくれるかもしれません。
1on1のテーマはたくさんあり、リーダーやマネージャー、上司の引き出しが多いほど、話しやすい話題を部下やメンバーに振りやすくなります。
1on1で話すことについて具体的なテーマ例を知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
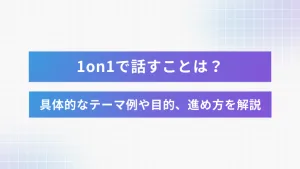
1on1を苦痛にするやってはいけないこと
1on1が苦痛にならないようにするには、やってはいけないことを理解しておくことも重要です。よかれと思ってやっていることが逆効果になっているかもしれません。
1on1を苦痛にするやってはいけないことは下記の通りです。
ほかの人と比較する
「〇〇さんはできているから、君もできるはず」というように、ほかの部下やメンバーと比較することは逆効果です。
劣等感を刺激してストレスを与える恐れがあります。
突然開催する
部下やメンバーは1on1に向けて話すことや提案、議題などを準備して臨みます。
突然開催されると準備不足で的外れな言動が多くなり、1on1が終わったあとに落ち込んでしまうかもしれません。
雑談ばかりする
部下やメンバーによっては、残業が発生しないようにギリギリのスケジュールでタスクをこなしている場合があります。
1on1で雑談ばかりされると、生産性の低い時間に対して苦痛を感じる可能性が高いです。
説教をする
目下の者に対してくどくど小言や忠告を述べるのは、1on1ではやってはいけないことです。雑談と同様に部下やメンバーの貴重な時間を奪うことになります。
どうしても伝えることが多い場合は、1on1で話す必要がない議題については別途チャットやメールで共有しましょう。
1on1で部下やメンバーに苦痛やストレスを与える失敗例
1on1で部下やメンバーに苦痛やストレスを与えないようにするには失敗例も参考になります。
部下やメンバーに苦痛やストレスを与える典型的な失敗例は下記の通りです。
- 話す内容が途中でなくなって沈黙が訪れる
- 突然1on1のスケジュールが変更になる
- 前回話した内容、指示したことを忘れてしまう
- 優先順位が低い議題について長く話してしまう
- 気づけば自分ばかり話している
- 進捗や成果の報告ばかりを求めてしまう
- 部下やメンバーの提案を結局採用しない
- 自慢話をだらだら聞かせてしまう
- 1on1の頻度が多く肝心の業務時間が減っている
- 明らかに達成できない目標を設定してしまう etc.
1on1の失敗例は挙げるときりがないほど多いです。実施者が気づかぬうちに苦痛やストレスを与えて、1on1が失敗しているケースもあります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規とはいえ、部下やメンバーは上司や先輩に不満を言いづらいです。実施者が配慮しても失敗に気づきづらいですよね。
匿名のアンケートを導入して部下やメンバーの不満を吸い上げ、実施者以外が客観的に1on1をモニタリングするとよいでしょう。
1on1で部下やメンバーに苦痛を与えないためにはコーチングを学ぶのがおすすめ
リーダーやマネージャー、上司が1on1で部下やメンバーに苦痛を与えないようにするには、コーチングを学ぶのがおすすめです。
コーチングでは、相手の意思や考え、価値観を尊重しつつ、目標設定から目標達成までを支援します。
ヒアリングを基調とした双方向のコミュニケーションなので、一方的で高圧的な指導や説教になりづらく、部下やメンバーが安心して話せます。
コーチングを習得すれば、部下やメンバーに苦痛を与えることなく、1on1を実施しやすくなるでしょう。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規本音を聞ける可能性が高くなり、チームのためになる情報も得やすくなります。
コーチングの概要やコーチングを部下やメンバーのマネジメントに活かす考え方については下記の記事で学んでみてください。
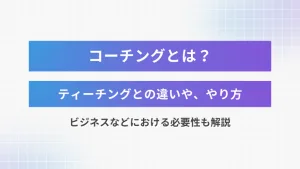
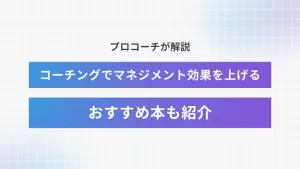
コーチングを学ぶのにおすすめのスクール

チームや組織のリーダーが1on1で部下やメンバーに苦痛を与えないようにするには、コーチングを学ぶのがおすすめだとお伝えしました。
ただ、コーチングを習得しても部下やメンバーとの信頼関係を築いて対等に話し合うのは簡単なことではありません。
1on1における対話のパフォーマンスを最大限に発揮するには、土台となる自身の人格と在り方まで磨き上げることが重要です。
CAM Japanでは、人格や在り方を磨きつつコーチングを学べる環境が整っています。自分自身と向き合い続けながら、傾聴や直観、行動設計といったコーチングスキルを習得していきます。
世界水準となる国際コーチング連盟ICFから認定されたスクールでもあり、部下やメンバーから信頼してもらえるICF資格を取得することも可能です。
コーチングに関する悩み、疑問を解決できる双方向型の無料説明会も開催しています。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規1on1のコミュニケーションに自信がない方、部下やメンバーの成長を真剣に後押ししたい方はぜひ参加してみてください。
結論|1on1の苦痛を減らすには双方向のコミュニケーションを学ぶことから始める
リーダーやマネージャー、上司からすると、1on1はメンバーや部下とじっくり話せる貴重な機会です。
ですが、1on1は知らないうちに部下やメンバーに苦痛を与え、パフォーマンスを下げる要因にもなりかねません。
常に1on1が苦痛になっていないかを振り返り、ストレスを与えない仕組みを模索することが大切です。
一方的な指導や命令が苦痛、ストレスの原因となりやすいので、実施者は双方向のコミュニケーションを心がける必要があります。双方向のコミュニケーションはコーチングを学ぶことで自然と行えるようになります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規1on1がうまくいかず悩んでいる方、これから1on1を始めようとしている方は、コーチングスキルの習得もぜひ検討してみてください!
1on1の苦痛に関するよくある質問
本記事を通して、1on1が部下やメンバーを苦痛に感じさせる原因と対策が分かり、実施の方向性を見直せたのではないでしょうか。
さらに1on1の苦痛を減らせるように、関連する疑問にQ&A形式で回答します。