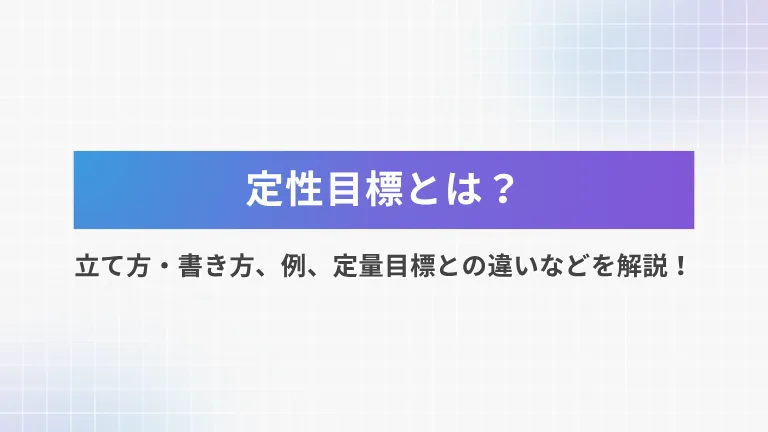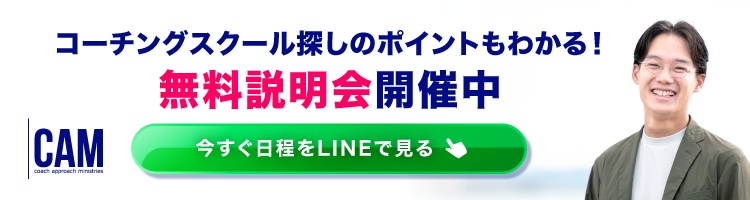理想のチームや組織、個人の成長を目指すには定性目標の設定が重要です。ただ、定性の意味を理解しなければ、どのような目標なのか正しく理解できません。
今回は定性の意味をおさらいしつつ、定性目標の概要や立て方、書き方、例などを解説します。
定量目標との違いにも触れているので、区別がついていない方もぜひ参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
- 定性目標とは数値ではあらわせない理想の状態、質、行動などを定める目標です。
- 定性目標の例としては「顧客の潜在ニーズに気づけるようになる」「AIで事務作業を効率化する」などの目標が挙げられます。
- 定性目標の立て方、書き方のポイントは、数字を使わないこと、課題から理想を言語化することです。
定性目標とは?
定性とは、性質を確かめることを意味する言葉です。
読み方は「ていせい」となっています。性質は基本的に数値で表すものではありません。
たとえば、人の性質は性格という言葉であらわし、「友好的」「思慮深い」「冷静」などの特徴であらわします。
定性の意味をふまえると、定性目標(英語:qualitative goals)とは数値ではあらわせない(数値化できない)理想の状態、質などを定める目標です。
数値化が難しい理想の行動を掲げるために設定されることもあり、行動目標と呼ばれることもあります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規定性目標を立てることで、チームや組織の一員として目指すべき方向性、望ましい行動、振る舞い、態度などを伝えやすくなるでしょう。
定性目標と定量目標の違い
定性目標の対義語にあたる言葉が定量目標です。
定量は、決まった量や決められた量、分量を確かめることなどの意味を持ちます。
定量の意味をふまえると、定量目標(英語:quantitative goal)は客観的に量で評価できるように数値で表す目標だと考えられます。
定性目標と違い言語化だけでなく数値化して表すのが一般的です。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規目標に数を設定することで、部下やメンバーが数値を高める(あるいは減らす)ための試行錯誤をスムーズに始めてくれるでしょう。
定性目標・定量目標の例
定性目標や定量目標の意味が分かり、それぞれの違いについてご理解いただけたのではないでしょうか。
さらに理解を深めるには各目標について具体例を知ることも重要です。
引き続き、定性目標と定量目標の例をそれぞれご紹介します。
定性目標の例
まずは定性目標の例を営業・接客業、事務・経理などのテーマで挙げてみます。
【営業・接客業に関する例】
- 顧客の潜在ニーズに気づけるようになる
- AIツールを活用したプレゼン資料の作成スキルを磨く
- チーム内で誰よりも業界のトレンドに詳しくなる
- 来店者が感動するような接客をする
- 難易度の高いマナーの資格を取得する
- クレームに毅然と対応できる冷静さを身につける etc.
【事務・経理に関する例】
- スピードと正確さを両立させた事務処理を心がける
- AIで事務作業を効率化する
- マニュアルを作成して無駄な質問を減らす
- 仕分け入力のミスを減らす
- 税制改正について理解を高める
- 不正な会計処理を撲滅する etc.
定量目標の例
続いて定量目標の例を営業・接客業、事務・経理などのテーマで挙げてみます。
【営業・接客業に関する例】
- 売上を〇円アップさせる
- 新規顧客開拓数〇件を目指す
- アポイント数〇件を目指す
- 来店者一人あたりの説明時間を〇分までに抑える
- 接客アンケートの全項目で評価〇以上を獲得する
- クレームの数を〇件までに抑える etc.
【事務・経理に関する例】
- 入力ミスの回数を月〇回までに抑える
- 印刷ミスによる書類の廃棄枚数を月〇枚までに抑える
- メール返信に要する時間を1回あたり〇分までに減らす
- 支払い期日の超過件数を〇件までに減らす
- 経費を〇%削減する
- 決算月の残業時間を〇時間短縮する etc.
定性目標の立て方・書き方のポイント
定性目標と定量目標の例を把握することで、定性目標の意味がより深く理解できたのではないでしょうか。
ただ、意味を理解しても実際に立て方や書き方などを知らないと、正しく目標を設定できないかもしれません。
ここでは、定性目標の立て方や書き方のポイントを解説します。
数字を使わない
定性目標の立て方や書き方のポイントの1つ目は数字を使わないことです。
基本的には目標に数字を含めると定性目標ではなく定量目標になりやすいです。
数字を使わないことを意識するだけで、定性目標を設定しやすくなります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規定性目標を設定するにあたって、定量目標を混同してしまいそうな方は、シンプルに数字を使わないという方針を徹底しましょう。
課題から理想を言語化する
定性目標の立て方や書き方のポイントの2つ目は課題から理想を言語化することです。
たとえば、リーダーや管理職が課題から理想を言語化して目標を立てる例は下記の通りです。
| 課題 | 理想 | 目標 |
|---|---|---|
| 会議で話さない人がいる | メンバーが積極的に発言する | 自分の意見や考えをはっきりさせて会議に参加する |
| メンバーからやる気が感じられない | メンバーが楽しそうに働いている | 創造力を発揮して仕事を楽しめるようにする |
| 仕事を抱え込むメンバーが多い | 仕事が多いときに同僚や上司に気軽に助けを求められる | 遠慮せずに周囲を頼れる組織を作る |
課題から連想される理想は定性目標を立てるときの材料になります。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規理想に基づき、伝わりやすい言葉やシンプルな表現を考えて、掲げるのに相応しい定性目標を作りましょう。
定性目標を設定するときの注意点
定性目標の立て方や書き方のポイントが分かり、組織やチームで早速設定してみたいと思ったリーダーや管理職の方もいるでしょう。
定性目標を設定するときにはいくつか注意点があります。
ここでは定性目標を設定するときの注意点を解説します。
評価基準が分かりづらい
定性目標は内容が抽象的になりやすく、評価基準が分かりづらい傾向があります。
「チームの生産性を高める」といった定性目標がよい例です。
生産性は数値であらわせず、人によって評価が変わる恐れがあります。
上司が評価を誤れば部下やメンバーのモチベーションが低下したり、反発を招いたりするかもしれません。
たとえば「表計算シートにプログラミングを導入して、自社向けの検索機能を開発した」など、生産性を高めるための行動を評価することが重要です。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規上司の立場として部下やメンバーが取り組んだ行動を見落とさないようにしましょう。
目標が形骸化しやすい
定性目標では目指す方向性を示せますが、人によっては具体的なアクションが思い浮かばず、行動につながらないこともあります。
いつの間にか目標が忘れられて形骸化するケースも珍しくありません。
形骸化を防ぐには、リーダーや管理職が目標に対して行動を起こして模範的な態度を示すだけでなく、目標に対する成果を確認できる体制を整備することが重要です。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規部下やメンバーの成果を確認するには1on1ミーティングが適しています。ただ、1on1ミーティングが苦痛になってしまう方もいる点には注意が必要です。
1on1ミーティングが苦痛になる原因と対策については下記の記事でご確認ください。
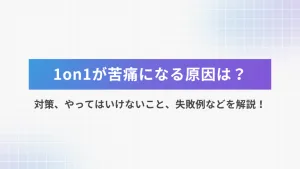
リーダー・管理職がメンバーの定性目標を管理するには?
定性目標は評価基準が分かりづらく、形骸化するリスクもありました。
リーダーや管理職の立場としては、目標を設定しても達成まで導けるか、不安を感じたかもしれません。
定性目標を適切に管理できるようになりたければコーチングの習得がおすすめです。
コーチングは、目標の設定から行動の実践まで評価も含めて管理する対話手法です。
マネジメントやリーダーの育成などにも活用されています。
コーチングでは、ヒアリングや質問によって対象者の現状を正しく把握して、無理なく取り組める目標を設定します。
起こした行動と結果に基づき必ずフィードバックをして、再び次のアクションにつなげる流れです。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規コーチングの一連の流れを習得すれば、部下やメンバーに適した定性目標を設定して、達成まで導いていけるでしょう。
コーチングの概要をはじめ、コーチングを目標設定やマネジメント、リーダーの育成に活かす考え方を知りたい方は、下記の記事もぜひ参考にしてみてください。
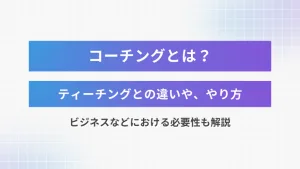
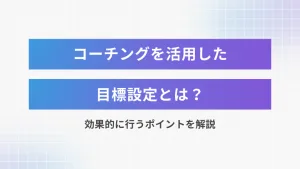
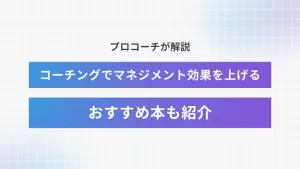
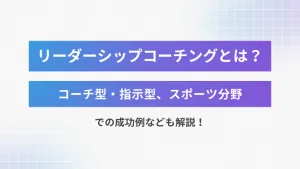
定性目標の設定から達成までを体感できるコーチングスクール

定性目標の設定から達成までのプロセスは、コーチングの習得で学べることをお伝えしました。
コーチングは独学でも学べますが、正しいカリキュラムで実践しなければ、部下やメンバーから信頼される本質的なスキルは習得できません。
正しい目標によって組織やチームを導けるリーダーや管理職を目指すなら、CAM Japanでコーチングを学んでみてはいかがでしょう。
CAM Japanは、世界水準となる国際コーチング連盟ICFの認定を受けた実践型コーチングスクールです。
受講生のそれぞれが目標を設定して、一人ひとりが目標に向けて進んでいくプロセスを体感しながら、コーチングを習得します。
無料説明会では直接プロコーチに質問できるので、コーチングに関する疑問や定性目標の立て方についても相談可能です。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規説明会参加特典として「本音を引き出す150の質問集」もプレゼントしています!定性目標を決める過程で部下やメンバーの本音を知るのにぜひ活用してみてくださいね。
結論|定性目標でチームや組織を理想の状態へ
定性目標を立てることは、リーダーや管理職、メンバーの間で、チームや組織の理想を共有することです。
一人ひとりがチームや組織のためにできる行動を考えるきっかけになります。
リーダーや管理職が理想のチーム、組織を作り上げるには、定性目標の設定、達成は不可欠です。
コーチングを習得すれば定性目標の設定から達成までのプロセスを正しく理解できます。
 ICF認定コーチ浅井元規
ICF認定コーチ浅井元規定性目標の立て方に自信がない方は特に、ぜひコーチングを学んでみてくださいね。
定性目標に関するよくある質問
本記事で定性目標の意味や立て方、書き方のポイントを理解できたのではないでしょうか。
さらに理解を深めるために定性目標に関するよくある質問にも回答します。