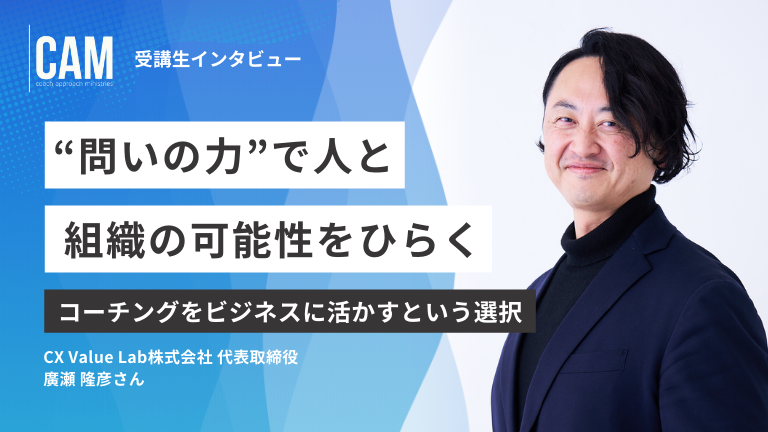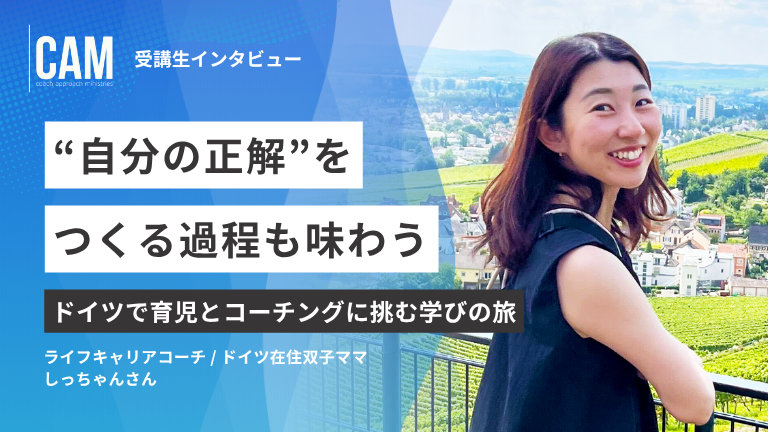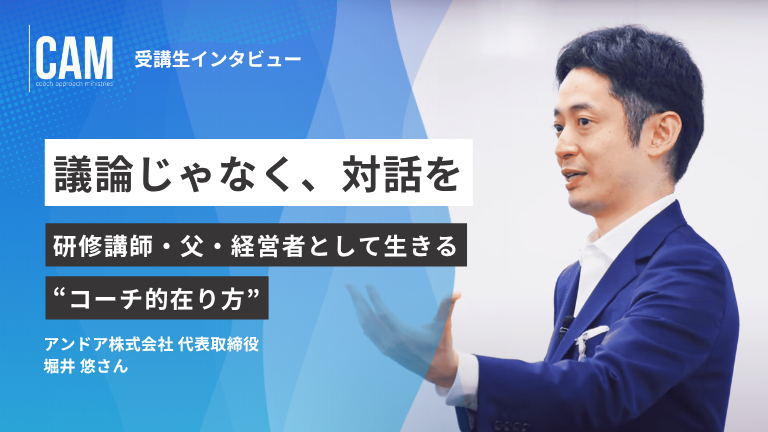コンサルタントとして経営やマーケティングの現場で数多くの企業を支援してきた、たかひこさん。
そんな彼が、さらなる“本質へのアプローチ”を模索する中で出会ったのが、CAM Japanでのコーチング学習でした。
コーチングの学びを通じて、「問い」の力が人や組織の可能性を引き出すと実感したたかひこさんに、仕事とコーチングの接点、そして実践を通して見えてきた変化について伺いました。
廣瀬 隆彦(ひろせ たかひこ)│CX Value Lab株式会社 代表取締役 マネージング・ディレクター
X:@hrstkhk
大学卒業後、現エイベックス株式会社に入社。安室奈美恵などのマーケティングや直販ECサイトの立ち上げなどを歴任後、株式会社WDI JAPANで日本におけるハードロックカフェなどのマーケティング責任者として売上に貢献。2018年には株式会社メルカリへ入社し、マネジメントとして、人材育成や業務品質・生産性向上などに貢献。その傍らで中小企業代表100名以上と接し感じた原体験から、中小企業と社会に役立つデザイン経営の推進とSociety5.0の実現を目的としたCX Value Lab株式会社をコロナ禍の2020年3月に設立。全国の中小企業のマーケティング支援、イノベーション・新規事業創出やベンチャー企業の経営戦略などを多数支援。
コーチングとの出会いは「問い」への探究心から
――コーチングに興味をもったきっかけを教えてください。
マーケティングや経営の支援をする中で、「顧客やクライアント自身が認識していないインサイト(深層心理)や背景をもっと知りたい」「表面的な言葉の裏にある本質を探りたい」と感じる場面が多くありました。特にマーケティングのユーザーリサーチにおける局面では、ロジカルに分析するだけでは深いインサイトに届かないという限界を感じていたんです。
お客様自身も、「なんでこの商品を買ったんですか?」って聞かれたらパッと答えられないことがあると思うんです。そこに「問い」があったら、お客様の中でも言語化できていなかった部分を深掘りできるのではないか。そう思ったときに、それってまさにコーチングのアプローチなのでは?と気づいたんです。
科学と体感、これまでの経験がつながったコーチングの学び
――実際にCAM Japanで学んでみて、印象に残っていることはありますか?
CAMの学びの中で印象的だったのが、脳の反応や心理的なメカニズムについても学べたことです。コーチングというものがこれほどアカデミックな視点からも体系化されているというのは知りませんでした。なぜその問いや対話が効果的なのか、科学的な視点も入った理論と実践の両面から理解できたことはとても良かったです。
――CAM Japanの学びの中で印象に残っているエピソードはありますか?
「人はもともとクリエイティブで、無限の可能性がある」という言葉には、とても納得しました。私は過去に挫折を味わって、「もう一回自分の人生考え直してみよう」と自分と向き合う時期を過ごしたことがあったのですが、そこから大学院での学びや起業経験を経て、自分自身の成長を実感していたので、この言葉は腑に落ちるなと思いました。
自分を変えることができたからこそ、人の可能性を信じられるようになりましたね。私の場合は挫折をきっかけに、自分と向き合わざるを得なかったという感じでしたが、コーチングという対話があれば、強烈な挫折体験とかがなくても自分と向き合うことができるなと思いました。
ビジネスの中で問いを活かす
――コーチングの学びを、どのようにお仕事に活かしていますか?
仕事柄、お客様へ投げかける「問い」の質がとても重要だと思っていますが、CAM Japanで学んだコーチングの視点や視座が、「問い」を考える上で非常に役立っています。たとえば、コンサルティング支援の中で、企業のパーパスやバリュー、ミッションの策定を支援する際には、経営者や社員の「まだ言語化されていない思い」を引き出すことが求められます。
事業承継をされた経営者に「創業者はどんな方でしたか?」と聞くことで、その事業をつないできた人々の価値観や組織のルーツが自然に浮かび上がってくることもあります。純粋なコーチングとは少し違いますが、「ことばになっていないだけで、そこにある思いや願い」を引き出すには、コーチングの視点がとても有効です。
――確かに、コーチングは「思考を刺激し続けるプロセス」ともいわれ、問いを通じた対話の中で、クライアントがこれまで考えたことのない領域に踏み込んでいく場面がよくありますね。
そうですね。ビジネスでは、コーチングで得た学びを活かしつつ、「問いの力」を高めることで、相手の内面や本音に触れながら、本質的な課題解決に近づけるのではないかと思っています。仕事でクライアントと対話する際にも、ことばになっていない思いや願いを表層に出せるような、橋渡しとなる問いを投げることを常に意識していますし、これからもまだまだ強化したいと思っています。
コーチングの価値を信じ、これから届けていきたいこと
――たかひこさんはご自身も経営者であり、また経営者の方をサポートするお立場でもある中でコーチングを学ばれてきていますが、経営者がコーチングを学ぶ、あるいは受けることにはどのような意義があると感じますか?
経営者がコーチングを学ぶことには、単なるスキル獲得以上の意義があると感じています。たとえば、問いを通して部下やチームメンバーの言語化されていない想いや、潜在的な価値観に触れられるようになります。報告だけではわからない本音や迷い、ビジョンを共有していくうえで、「問い」は非常に有効なツールです。
コーチングを受けることは、経営者自身が自分の内面を見つめ直し、より本質的な意思決定をしていくための支えにもなると思います。数年後に自分の事業がどうなっていたらいいか?ということは少しイメージしていても、そのときに自分はどうなっているのか?自分の半径数メートル以内の人たちはどんなことを感じ行動しているのか?ということまでは、意外と経営者の方でも考えていなかったりすると思うんです。
僕自身、コーチからそんなことを聞かれたらちょっとドキッとしてしまいます(笑)。でもそのようなところまで思いをめぐらせながら進んでいくことができたら、その方の思考や行動、そして他者に向けた関わりにもよりクリエイティブで本質的な思いや願いが反映された行動ができるようになる。コーチングを受けることも、学ぶことも、組織を率いる立場にある方ならば、一度は体験してみる価値があると思います。
――今後のビジョンについて教えてください。
みなさんがみなさんのペースで、自分の可能性を信じて、自分の中にあるクリエイティビティや想い、描いている世界をうまく言語化していけるような、そんなプロセスに寄り添いたいと思っています。そして、それが本人の行動や発信につながって、結果として自分自身が到達できる場所も変わってくる。そんな姿を一緒に描いていけたらと。そういう人々や組織が増えることで、社会ももっと良くなっていくんじゃないかと思っています。
自らが自身のポテンシャルを信じて成長することのお手伝いを、隣に立ってできるような存在でいられたら嬉しいです。
CAM Japanでは、コーチングについて知ることができ、コーチングに関する悩み、疑問なども解消できる双方向型の無料説明会を開催しています。
「自分にあったスクールを探したい!」「スクールを探しているけど、情報が多くて迷子…」という方から「コーチングはまだよくわからないけど、なんだか気になっている」という方まで、幅広くお気軽にご参加いただける場となっておりますので、ぜひこの機会をご活用ください。