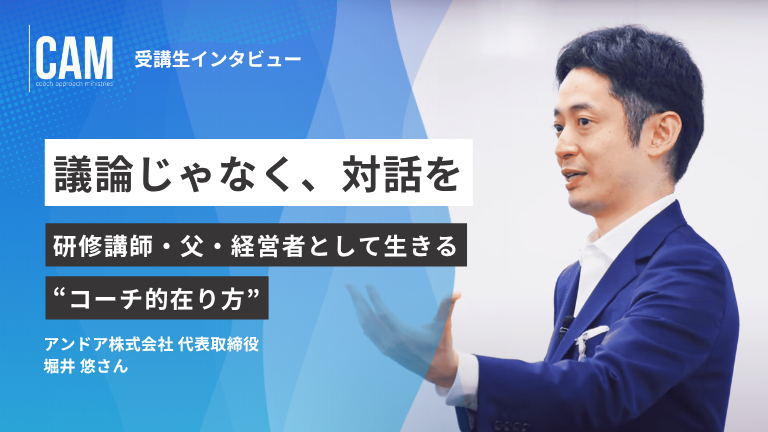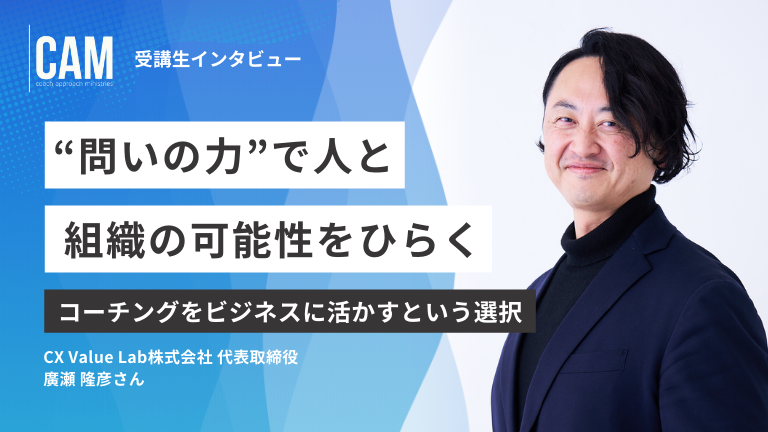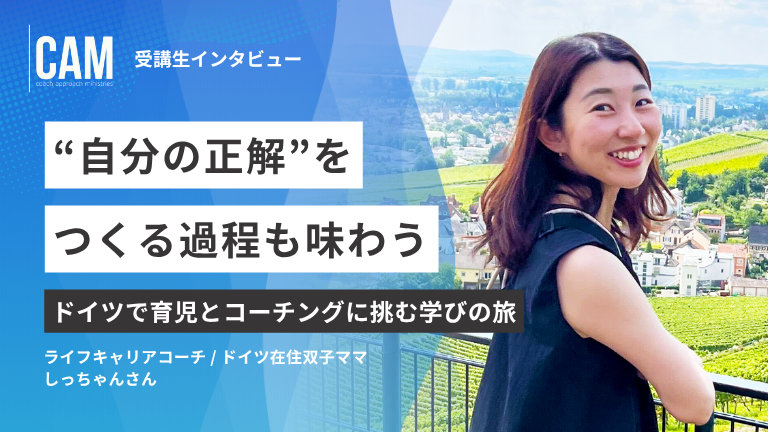法人向けの研修会社「アンドア株式会社」の経営と講師業を両立する堀井さん。
CAM Japanでの学びをきっかけに「対話」を軸とした独自の研修スタイルを築き、仕事にも家庭にもコーチングのエッセンスを取り入れながら、公私ともに“自分らしい関わり方”を模索・実践されています。
今回のインタビューでは、起業の決断に至った背景から、研修現場での葛藤、家族との関係性の変化まで、そのリアルな軌跡を伺いました。
堀井 悠(ほりい ひさし)│アンドア株式会社 代表取締役
X:@horiihisashi
慶應義塾大学総合政策学部卒業。組織の対話の質向上に特化した人材開発コンサルタント。スターバックス、リクルートなどを経歴し、会社のパーパスと個人の主体性を意味づける対話について豊富なファシリテーションの経験を持つ。大手自動車メーカー、製薬会社、内閣府、大阪市など累計500社以上で人材開発を経歴し、「腹割り対話」「きっかけ砂時計対話」などの独自メソッドを開発。マネジメントの失敗事例をデータベース化し、組織の問題を構造的に示す論理性と、落語を思わせる共感的な語り口で講師満足度平均96%をマーク。ミッションは誰もが「本来の力を、思いのままに」できること。
起業のきっかけは、授業中のコーチングセッションだった
――現在はどのようなお仕事やライフスタイルを送られていますか?
今は「アンドア株式会社」という法人向けの研修会社を経営しています。今年で4期目に入り、講師として現場にも立ちつつ、経営も担っています。この会社を立ち上げるかどうかを決めたのが、実はCAM Japanでの最初の授業のときで──というのも、最初の課題が「コーチングを体験してみよう」という内容だったんですよ。
当時、浅井さんに体験セッションをお願いして、「ちょっと重めのテーマでもいいですか?」と起業について相談したところ、自分の中にあった“本当は起業したい”という気持ちが見事にあぶり出されて。「あ、もう起業したいんだな、自分」って明確に分かって、それが決定打になりました。
その後、会社として「何を強みにするか?」を3年間かけて模索しながら、ようやく見えてきた答えが「対話」でした。多くの組織では、“議論”や“会議”はあっても、“対話”がきちんと存在していない。対話がないことで、創造性や自発性が奪われてしまっている現場をたくさん見てきました。だからこそ、僕たちは「議論ではなく、対話に特化する」ことを会社の軸にして、研修を展開しています。
プライベートでは、子どもが2人いまして、上の子が小学2年生、下の子が4歳の年中です。仕事は忙しいんですが、週末はなるべく家族と過ごすようにしています。最近は娘たちと一緒に料理するのが楽しくて、生パスタを粉からこねて作ったりしています。休日の大半は、公園に行ったり料理をしたり、家族との時間を楽しんでいます。
導くのではなく、ともに歩く──「お散歩する伴走者」という“在り方”
――CAM Japanで印象に残っている学びは何ですか?
いろんな授業を受けてきましたが、いちばん印象に残っているのは「コーチの在り方」です。スキルや理論ももちろん学びましたが、最終的に自分の仕事や関わり方に深く染み込んでいるのは、あの「在り方」の授業なんですよね。
僕は研修講師として、時には企業の不正問題など、ちょっと厳しい場面に切り込まないといけないこともあります。でも今では、追い詰めたり正そうとしたりするのではなく、「この人は本当は何を望んでいるんだろう?」と関心を向けることが、自分の中で大事な軸になっています。
「合ってる、間違ってる」とか、「正しい方向に導かなきゃ」という姿勢ではなく、本当に“横でお散歩しながら”一緒に「ベストな行き先って何だろうね」と探っていくような、そんな寄り添う存在でいたい。これは授業の中で印象的だった比喩なんですが、いまでも仕事中、心の中で何度も言い聞かせている言葉です。その姿勢こそが、今の自分の仕事の中で最も価値を感じている部分ですね。
それに加えて、「自分の中の声に気づく」という感覚も、CAM Japanでの学びの中ですごく大事にされていたなと感じています。僕自身、コーチング関連の本などを読む中で「直感が大事」っていうのは頭では理解していたつもりでした。でも読むだけでは、それがどんなものかは分からなかったと思います。CAM Japanの授業があったからこそ、体験的に「ああ、やっぱりそうなんだ」と腑に落ちたんですよね。自分の違和感や直感に気づけるようになったのは、まさにCAM Japanでの学びがあったからだと思っています。
違和感を無視しない。自分の内なる声に耳を澄ませた「実験」の始まり
――CAM Japanでの学びによっての変化や、葛藤はありましたか?
変化は確実にありましたし、それに伴う葛藤もすごく大きかったです。たとえば以前は、新入社員への研修なんかでは、プロの厳しさを伝えることが必要だとされていて、企業の人事側からも「そういうスタイルでお願いします」と言われることが多かったんです。言い方はよくないですが、上から下に押さえつけるようなフィードバックが“良いもの”とされる風潮があったんですね。
実は僕も、そういったスタイルの研修をCAM Japanに通いながらも続けていました。ただ、やるたびに「なんか違う」「これ、本当はコーチングの思想から外れているんじゃないか」と、どこかでずっと矛盾を感じていたんです。でも、毎年オーダーが来て、仕事としては成立している。そんな現実もある中で、「仕事だからしょうがない」と割り切ってやっていた時期がありました。
でもね、自分の中の声──直感とも言えるかもしれませんが──やっぱりその違和感は拭えなかったんです。フィードバックを受けた受講者の顔が曇っている。全然晴れやかじゃない。それを見て、「この違和感を抱えたまま、あと10年やるのか?」という問いが、自分の中から湧いてきたんです。
「いや、そうじゃない。もっと信じられるスタイルがあるはずだ」「だったら試してみるしかない」と、自分の中でまさに“セルフコーチング”をするようにして、思い切って“実験”してみることにしました。
――実際に”実験”をしてみて、現場ではどんな変化があったのでしょうか?
研修の中で、厳しく押しつけるのではなくて、「ニコニコしながら、でも本気で関わる」というスタイルに切り替えていったんです。最初は取引先や仲間から「堀井さん、ちょっとぬるくなったんじゃないですか」「もう少し真剣さ出せませんか」と言われることもありました。
でも僕は「いや、大丈夫。結果で示すから」と返して続けました。すると実際に、受講者の成長や反応が目に見えて変わっていったんです。「次はもっと良いものをつくります!」「お客様の信頼を超えるビジネスパーソンになりたいです」と、受講者自ら本気で取り組むようになっていったんですね。
そのとき、「ああ、自分が本当に信じたい関わり方で良かったんだ」と、確かな手応えと確信を持てるようになりました。
幸せって何?──“美味しくご飯を食べる”から始まる人生哲学
――CAM Japanで学んだことは、ご家庭や子育てにも活かされていますか?

はい。子どもとの関わり方は、すごく大きく変わりました。僕はもともと塾業界にいたこともあって、ある程度“強制力”を持って勉強させる技術もありました。でも今は、「今しかできないことに全力で」という考え方を大事にしています。
たとえば、小学生のうちは点数や順位よりも、友だちをたくさんつくることのほうが大切だと考えるようになって、「今日は誰と遊んだ?」「何が楽しかった?」といった会話を日々重ねています。問い方ひとつで、子ども自身の感情表現や行動が変わるんですよね。
コーチングで学んだ問いのスキルとして、「お友だちのどんなところを尊敬してるの?」「明日、後悔しないために今日はどう過ごしたい?」といった質問を子どもに投げかけることも増えました。そうすると、自然と子どもが自分で考えて行動するようになるんです。
あるとき、「宿題やってから食べるご飯と、やらなきゃって思いながら食べるご飯、どっちが美味しいと思う?」って聞いたら、「宿題やってからがいい!」って即答してくれて。「そうか、じゃあやろう!」って。問いを通じて、行動の選択を本人が自然にできるようになる。コーチングの“問いの力”は、まさに家庭の中でも活きています。
こうした関わり方は、妻との関係にも影響しています。最初は「習い事させなくて大丈夫かな?」「うちの子が他の子と違って見えたらどうしよう」といった不安もあったと思います。でも、僕たちの間では「本当に大事なことってなんだろう?」という問いを立てて、たとえば「将来、子どもが家を出ていくときにどんな言葉を残してくれたら嬉しいか?」と考えると、「友だちいっぱいできて、毎日楽しかった」と言ってくれることのほうがずっと嬉しいよね、という結論に至ったんです。
そういう問いを共有しながら、対話を重ねていくうちに、妻の中の迷いも少しずつ晴れていって、今ではお互いに同じ方向を見ながら子育てができていると感じています。本質は何か?を問いながら、家族の在り方を一緒に考えていくことで、自然と今大切にしたいことが見えてくるようになりました。
――CAM Japanで学ばれている最中に、入院されたことも一つの転換点だったと伺いました。
そうなんです。実はCAM Japanに通っていた頃に、腰のヘルニアが悪化して、2021年の1月に大学病院で手術を受けました。しばらく動けない時期があって、痛みや不安とも向き合いながら、ずっと「自分にとっての幸せって何なんだろう?」という問いを何度も何度も反芻していたんです。
そしてたどり着いたのが、「美味しくご飯を食べられること」でした。高級な食事である必要はまったくなくて、家族と一緒に生パスタを手作りして「うまいね」って言いながら囲む食卓。休日に昼から3時間かけて作って、うまくいった日もあればいかない日もあるけれど、「今日もいい時間だったな」「美味しいご飯だったな」と思えたら、それで十分幸せなんじゃないかと。
仕事でも同じです。適当にやり過ごした日のご飯は味気ない。でも、「今日、ちゃんとやり切った」と思える日のご飯は、やっぱり美味しい。だから今では会社でも、「結局、幸せって何かといったら、美味しくご飯を食べられることだと思うんだよね」「美味しいご飯を食べるために、今できることを全力でやっていこうぜ」とよく話しています。
売上や成果ももちろん大事です。でもその前に、「本当にこのご飯、うまいか?」という問いを持てるかどうか。その問いがあれば、子育ても、仕事も、人生そのものも、もっと豊かにできると信じています。
こういう考え方ができるようになったのも、CAM Japanで“コーチとしての在り方”を学び、自分と向き合い、自分の声を聴くという体験を積み重ねてきたからこそだと思っています。
本来の力を、思いのままに──「対話」で広げる未来のビジョン
――今後の展望や、実現していきたいビジョンがあれば教えてください。
はい。これは自分の会社のビジョンとも重なるんですが、掲げている言葉が「本来の力を、思いのままに」なんです。働くあらゆる人たちが、自分の中にある本来の力を思いのままに発揮できる。そんな職場や社会をつくっていきたいと思っています。
これまでたくさんの人材育成の現場に関わってきて、一人ひとりと向き合うたびに感じるのは、「本当はもっといろんな可能性がある人なのに、それが組織の中に入ると見えなくなってしまう」ということです。役職や年齢、環境に影響されて「もう今さら…」って自分にフタをしてしまっている。それってすごく、もったいないと思うんですよね。
そういう人たちが、自分の可能性を諦めずに、自分らしい働き方や表現を取り戻していく。そのサポートをしていくために、僕ができるのは「対話の場をひらくこと」だと思っています。
――「対話」がカギなんですね。
はい。CAM Japanでの学びを自分なりに統合してみたときに、やっぱり「議論じゃなくて、対話だな」と強く感じたんです。仕事でも家庭でも、人生を動かすのは“正しい答え”を出すことではなく、“本当の声”を聴き合うことだなと。
CAM Japanではコーチングを通じて、人間という存在に自然に寄り添いながら、本来の力を発揮したり、自分の言葉で語る楽しさを体験できたと思っています。僕はそれを「対話」というレイヤーで社会に広げていきたいんです。企業や組織の中でも、議論ではなく対話を楽しむ文化が根づいていけば、クリエイティビティやその人らしい目標が自然と立ち上がって、「仕事が面白い」と感じられる状態が生まれると信じています。
だからこれからは、「対話といえばアンドアだよね」と言ってもらえるような存在を目指して、対話に特化した研修やプログラムをもっと広げていきたいと思っています。
――お話を伺っていて、コーチとしての在り方が、ご家庭やお仕事、そして日々の暮らし全体に、自然と息づいているように感じました。
ありがとうございます。そうですね、ぜひこれはこれからCAM Japanで学ばれる方にお伝えしたいんですが、CAM Japanの学びって、「スキルを学ぶ」「勉強する」っていう入口で入っても全然いいと思うんです。
でも僕自身、最終的にすごく実感しているのは、これはもう“スポーツ”みたいなものだということ。やってみないと分からないし、フィールドに立って何度も試していく中で、自分の体に馴染んでくるものなんですよ。続けるうちに、だんだん「これは日常そのもの、人生そのものなんだな」って感じるようになりました。
だから、コーチングを「スキル」として、自分の外側にあるもの、身につけるものとして切り離して考えるだけじゃなくて、「どうやって自分の暮らしや人との関わりに溶け込ませていこうか?」って。そんなふうに、ワクワクした気持ちで向き合ってもらえると、きっと素敵な学びになると思いますね。
CAM Japanでは、コーチングについて知ることができ、コーチングに関する悩み、疑問なども解消できる双方向型の無料説明会を開催しています。
「自分にあったスクールを探したい!」「スクールを探しているけど、情報が多くて迷子…」という方から「コーチングはまだよくわからないけど、なんだか気になっている」という方まで、幅広くお気軽にご参加いただける場となっておりますので、ぜひこの機会をご活用ください。