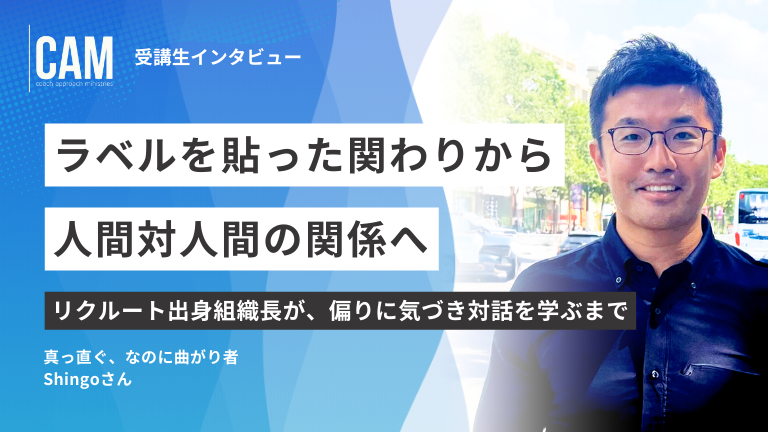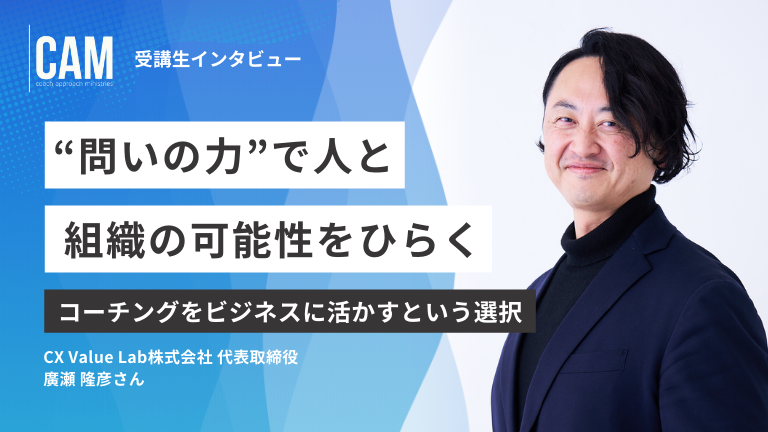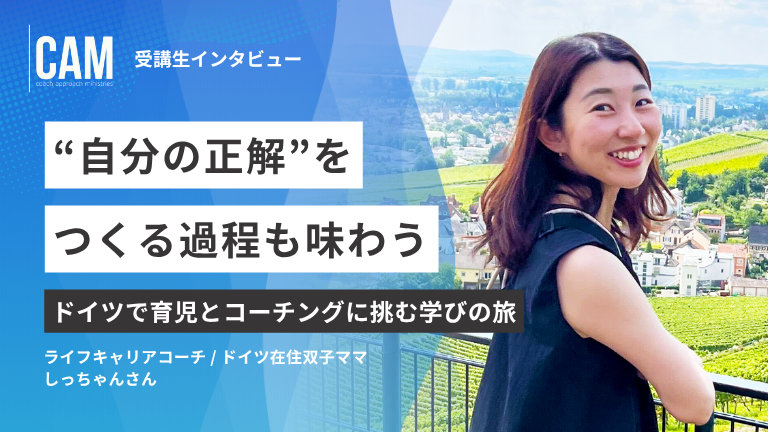マネジメント経験のなかで「自分のやり方が通じない相手がいる」と気づいたShingoさん。
多様なバックグラウンドのメンバーを束ねる組織長として、二児の父として、コーチングの学びと共に人との関わりの中で向き合ったのは「自分自身の偏り」でした。
CAM Japanでの学びが、仕事や家庭にどんな変化をもたらしたのか。その軌跡を伺いました。
Shingo│真っ直ぐ、なのに曲がり者
前職のリクルートでは、経理・財務部門の中核として12年間在籍し、決算開示実務・IPOやM&Aなど組織再編、グローバルファイナンス・ガバナンス体制の構築・運営を推進。 キャリア初期はグローバル会計ファーム(Ernst & Young)で不動産・金融業界を中心に、5年間にわたり会計監査およびアドバイザリー業務に従事。 企業の成長フェーズにおけるファイナンス領域と、組織・人材マネジメントを強みとする。2020年より英国ロンドン在住。
多様性の中で働き、家族と過ごすロンドンの暮らし
――今はどんな暮らしをされているのですか?
現在はロンドンに拠点を置きながら、多様な文化・言語・価値観の中で仕事をしています。家族も一緒にロンドンで暮らしていて、子どもが2人います。
最近は筋トレにハマっていて、1ヶ月ほど前からダイエットプログラムを始めました。旅行も趣味で好きですし、暮らしと仕事の両面で充実した毎日を過ごしています。
リクルートでの「通じないマネジメント」に直面して
──コーチングを学ぼうと思ったきっかけを教えてください。
前職はリクルートホールディングスで、12年間勤めました。当初は3年で辞めるつもりが、気づけば4倍の年月を過ごしていたことになります。
その中でマネージャーとしての仕事にも就きましたけれども、あるとき気づいたんです。「僕のマネジメントは“リクルートっぽい人”には通じるけど、それ以外の人にはまったくはまらないな」って。
僕のマネジメントではまる人って、技術を教えるというよりも、コミュニケーションの中で彼らの可能性とか働き方、パフォーマンスがぐっと変わっていくという感じだったのですが、会社がグローバル化し、新卒一括採用から中途や外国籍の社員が増える中で、これまでのやり方が通じなくなってきているのを感じました。
何でだろうと考えてみた時に、「きっとコミュニケーションのやり方なんだな」って思って。だから単なるテクニックの模倣というよりも、人の信念というか、根本から人と向き合うコミュニケーションのスキルが必要だと感じていました。そうこうする中で出会ったのがコーチングでした。
自分の「偏り」に気づいた統合クラス
──CAM Japanでの学びの中で、印象的だったことはありますか?
特に印象に残っているのが「コーチ的コミュニケーション統合」のクラスです。
CAM Japanに入った当初は、「引き出しとしてのスキル」を求めてしまっていたと思うんですよね。そんな中で、コーチ的コミュニケーション統合のクラスでは、スキルというよりも自分自身にフォーカスが当たった学びが強くありました。僕にとってはもう衝撃だったんですけれども、「あ、自分にはものすごく偏りがある。自分の考えや見方は偏っている」っていうことに気づかされたんです。
そして同時に、「みんな同じように偏りや信念、価値観というものをそれぞれにもっているんだな。そこには、誰かが悪いとかいいとかはない。ただそういった偏りが誰にでもそれぞれあるんだ」と思いました。これを認識することは、マネージャーとして本当に必要なことだろうなと気づけたのが大きかったですね。
だから、最初はスキルを求めて学び始めましたけども、僕が本当に欲しかったのは、自分に対しての内省や振り返り、自分の見方に偏りやバイアスがかかっているんだと気づくことだったのだと思います。
マネージャーとしては、その偏りを、「自分だって完璧じゃないし、他の人も誰しも完璧じゃないんだし」という風に受け取って、「完璧じゃないからこそ伸び代があるんだから、そこをどういう風に相手にコミュニケーションしていくか」っていう向き合い方に変わっていったような気がします。
──その偏りに気づいて変化していく中で、葛藤や苦しさはありましたか?
正直、気づいた瞬間は「なんで今まで気づかなかったんだろう」と思ったくらいで、抵抗や葛藤は少なかったですね。それは僕の性格的な部分もあったと思いますけれども、どちらかというと、気づいたことで「肩の荷が降りた」という感じがしました。むしろ、気づくまでは苦しさがあってもがいていたんだろうと思います。
それまでの僕は多分、リクルートで学んだマネジメントに強い自信、というか過信があったから、「このマネジメントスタイルは正しい」と思い込んでいた。染まりすぎていたというんでしょうかね。自分のマネジメントスタイルは好きだなとも思っていたんです。
それなのに、会社の環境の変化とともにマネジメントスタイルが通じなくなっていく。それでもこれまでのやり方を捨てられない。それが苦しかった。
それで、スキルを身につけていかなくちゃいけないだろうと思っていたんですけども、コーチ的コミュニケーション統合のクラスで自分と向き合うという経験をしたら、スキルを身につけようという考え方自体がひっくり返されました。助けてもらったなという感じがしています。
「諦め」ではなく「受け入れる」
──考え方自体がひっくり返ったことで、実際にどんな変化が起きましたか?
まずは、当たり前のことではあるんですけども、「みんな完璧じゃないんだな」って思えるようになりました。それを本当に受け入れられるようになったということかもしれないですね。
例えばCAM Japanに入る前の僕は、職場の上司や役員のようないわゆるえらい立場の人たちが「仕事に個人的なことを持ち込む、私利私欲を入れる」ということを、潔癖だと思うくらいに嫌っていたんです。そういうことをする人が許せなかったですね。
でも、現実はそういうこともありますよね。僕から見たら私利私欲に見えるだけで、他の人からは違った見え方をしているものもあるでしょうし。
それなのに、僕の中で勝手に「あの人は個人的な何かを達成するためにやっているんだ。それはおかしい」みたいなことを決めつけて、ばっさり切り捨てていた感じだったんです。
多分視野が狭くて、同じ価値観や信念でない人を受け付けない、物事の捉え方に偏りのある人間だったと思います。「通じないから、諦めよう」「もういいわ」みたいにも思っていました。
でも、CAM Japanで学んでからは、「みんなそれぞれの人生でいろんな経験をして、これまでの良かったことや苦しかったこと、失敗したこととか様々なことが根っこにあるんだな。時には何かを守るために、時には過去の成功体験から、それに倣いながら物事を進めているだけだな」と思うようになりました。
人それぞれにそれぞれの正義・信念みたいなものがあってやっているから、それが僕とは違うやり方だったとしても、そもそも僕はそれをジャッジをする立場じゃないし、ジャッジするようなものでもないなっていう風に。
「みんなそれぞれいろんな考えや思いがあるんだな」っていうことに気づかせてもらったので、リラックスできるようになりましたね。もちろん今でもイライラすることはありますけども、物事が進まないということがあっても受け入れられるようになりました。
以前のような、「諦めよう」っていう切り捨て系の感じでいると、僕の世界はどんどんと縮まって小さくなってしまうと思うんです。でも、今は考え方を変えられたおかげで、世界が小さくなるのではなくて、自分の心地よさを理解しながらも、それ以外の部分や全体を見れるようになったかなと思いますね。
──ご自身と向き合うこと以外で、コーチングの学びがお仕事に活かされていると感じるのはどんな時ですか?
「コーチングと脳科学」のクラスは、僕自身が定量的な考え方で物事を整理するのが好きなタイプなので、はまりましたね。
感覚で説明されるとなんとなく分かることを、科学的に、脳の回路の話なども含めてやってくださったので。コーチングにおいても、マネジメントにおいても、再現性のあるものにしていくために意識するとよいことをを確認できたと思います。
あと、「コーチングと3つの変化」のクラスは、人の”変化”について、”変化”、”転換”、”変革”という3つの視点から考えるクラスですけれども、僕は最初全然わかんなかったんです。「なんなんだろうこれ?」って思っていました。
でも6回目か7回目の授業でようやく繋がってきました。「相手が今”変化”を求めているのか?”転換”のタイミングにいるのか?それとももうあとは”変革”なのか?」っていうことを意識したり理解したりしながらコミュニケーションすると、結果が全然変わるなっていうことがわかってとてもよかったですね。
それから、コーチングのコミュニケーションの在り方の一つには、”傾聴”がありますけれども、仕事で会社のメンバーとの1on1をする時に、僕はこっそり傾聴を意識して集中して聞くんです。
そうすると相手のコンディションとか、「なんでその言葉を発したんだろう」っていうのを頭に留められる気がしています。それを頭に留めてメモしておくと、徐々に本人の勘所、関心どころみたいなことが分かりやすくなってきて、何をどう伝えればいいかとか、仕事をする上での相手のドライバーはどこにあるのかっていうこともわかってくるので、コミュニケーションしやすくなるなということに気づきました。
今、僕が一緒に仕事をしている方達はいろんなバックグラウンドをもっていて、日本人はマイノリティで、みなさん国籍もさまざまです。
だからちゃんと、相手の言語も考え方も理解しながら、どこを押せばどう動いてくれるのかっていうことを試す。実は今、そんな実験みたいなことをしているんです。実験の結果が出てるのかって言われると、人によってばらつきがあるんですけれども、「どういう風にコミュニケーションして、どんなことを聞いていくと、反応が見え、大きく物事が進むのか」ということを試行錯誤しています。
「ラベルを貼った」関わりから、「人間対人間の関係」へ
──ご家族、ご友人との関係で気付いたことは何ですか?
これはですね、相手に興味を持ってしっかり本当に傾聴してみると、いろんな発見があるんです。それをやってみるかやってみないかで、全然関係性が変わるなと思います。
僕はどうしても普段のコミュニケーションで、「”親”と”子供”」や「”妻”と”夫”」という風にラベルが出てきていたんですよ。そうすると自然と立場みたいなものが作られていって、方向が見えちゃってるコミュニケーションになりがちだったんです。予定調和というか。
それぞれの立場で喋ることも、それはそれで大事なんだと思うんですけれども。でも「その言葉を発した背景にあるものは何か」とか、「いま何を相手が考えてるのか」とか、立場よりもそういうことに意識や好奇心を向けた「人間対人間のコミュニケーション」っていうものができてなかったなと気づきました。
──「ラベルを貼っている」ことに気づいたきっかけは何でしたか?
とある受講生さんとの相互コーチングの時だったと思うのですが、「お子さんにとってそれが楽しいのはなぜなのか、本人達に聞いてみないんですか?」みたいな問いをもらった時にハッとさせられたんです。
僕は親という立場もあるし、ある程度自分が色々な経験を経てきているから、例えばゲームでもテレビでも「これをずっと続けてたら将来こうなる(よくないイメージ)」みたいな典型的な思い込みをしていたんだと思うんですね。なので、その状態の僕の言葉はきっと、子どもたちとってはリスペクトされてないような感じに聞こえていた。
一方で、サッカー好きの娘とサッカーの話をしているときは、おなじような立ち位置で、おなじように喋っているからめちゃくちゃ盛り上がるんですね。同様に息子に対しても、息子が好きなものを聞いてみたり、一緒にやってみたりすると、そこで会話が弾んでいくんです。
子どもたちが何を楽しんでいるのか、なんで楽しいのかを聞いて、もしくは一緒にやってみることで僕にも発見があって。ラベルを取り払って、子どもたちと同じ立ち位置でフラットにコミュニケーションをしていると、会話がこんなに変わるんだっていうのに気づけました。
コミュニケーションもコーチングも、磨き続けていきたい
──コーチングの学びを日常やお仕事でのコミュニケーションに活かされてきたShingoさんですが、これからさらに探求したいことは何ですか?
はい、2つありまして。
1つは、普段の仕事や生活の中で、僕も含めみんなが持っているバイアス、偏りや諦めに近い固定観念を解き放ってあげて、本人たちがやりたいこと、実現したいことに集中できるようなコミュニケーションができると最高だなって思います。なので、毎日色々なやり方で、色々なシチュエーションでコミュニケーションを試行錯誤するということを続けたいと思います。
もう1つは、CAM Japanで学んでみて、やっぱりコーチングというものはいいなと思いましたので。コーチングは、ある条件や状況に置かれている人にとってはとても効果的だと思うので、自分のコーチングをより良いものになるように磨いていって、コーチングという存在を必要としている人に届けられるようになっていけるといいなと思っています。
どんな形でやるのかはまだはっきりしていないんですけども、仕事以外のフィールドで貢献できたら、自分の人生という意味では嬉しいかなと思います。
多分僕は、いろんな人の話を聞くのが好きなのかもしれないですね。だから、ただ聞くだけではなくて、もうちょっとちゃんと技術を持った上で、相手にとってもメリットがある形で聞くことができるといいなと思っているのかもしれません。
学ぶ人へのメッセージ──「今」を味わうことの大切さ
──これからコーチングを学ぶ人や、今まさに葛藤している受講生に伝えたいことはありますか?
うーん、難しいですけれど…「”今をちゃんと楽しむ”ということはやった方がいい」ですかね。
コーチングを学ぶ上で、もちろん、「もっとこうなりたい」とか「学んだ先にこんな意味がある」とか、先々のことを人間誰でも考えるんでしょうけども。でもそれによって、せっかく目の前にある貴重なプログラムやセッションが、効果半減、もしくは相当失われることもあるかなと思うんですね。
たとえば、「これに何の意味があるんだろうか?」と思いながら学ぶのは、「意味がないといけない」という思い込みとか心配とかからきているのかもしれないですよね。でも僕は、目の前にあるものに一旦100%向き合ったら、意味や価値というのは、絶対に後で“もの”として残ってくると思います。
どのクラスの学びも、どんな経験も、ちゃんと今に集中してそこに向き合ってみたら、みなさんきっと僕よりももっと得られるものがあると思いますよ、というメッセージになるでしょうか。
「言うのは易し」なんですけれどもね。でも、絶対後になって10倍にも50倍にも変わると思います。
目の前のことに集中して向き合ったら、学びの残り方というか、学んだ先のコーチとしての在り方や個人の人生に大きくつながる気がするので。心配とか気になることはあるかもしれないですけども、それを一旦横に置いて、ぜひ目の前の学びに集中して楽しんでみてください。
CAM Japanでは、コーチングについて知ることができ、コーチングに関する悩み、疑問なども解消できる双方向型の無料説明会を開催しています。
「自分にあったスクールを探したい!」「スクールを探しているけど、情報が多くて迷子…」という方から「コーチングはまだよくわからないけど、なんだか気になっている」という方まで、幅広くお気軽にご参加いただける場となっておりますので、ぜひこの機会をご活用ください。